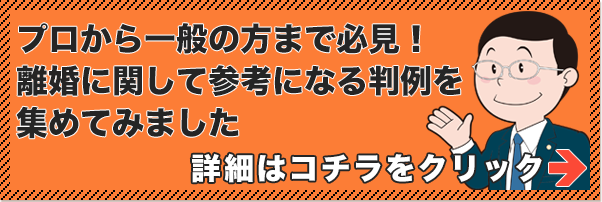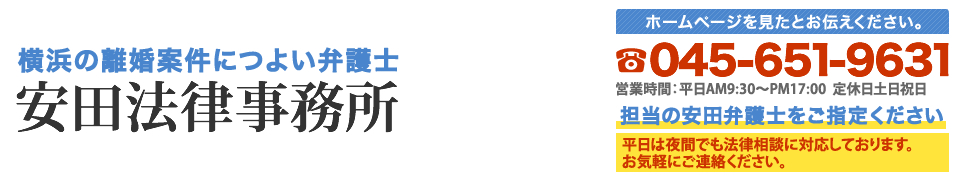東京高裁平成29年11月9日決定(判例時報2364)
■事案
事案や裁判内容は簡略化しています。
平成15年,父と母は別居しました。当時6歳と3歳の子がいました。
平成20年,離婚裁判の判決が確定し,2人の子の親権者は母,父は養育費として1人当たり月額5万円を成人に達する日まで払うことになりました。
平成21年,父は再婚し,再婚相手との間に2人の子がいます。 平成21年,父は自己破産し,養育費の免除を求める調停を申し立てました。
平成22年,養育費を減額する調停が成立し,父は養育費として月額4万円を払うことになりました。
平成24年,母は子が中学生になったので養育費増額を求めて調停を申し立てました。
平成25年,母は子を私立大学の付属高校に進学させました。父はこの進学に先立ち,私立学校に進学することに反対し,進学費用の負担要求にも応じませんでした。 母は子の大学進学が確定したことを根拠に養育費の増額と終期の延長を家裁で求めましたが,父は私学進学に反対し成人後の養育費負担にも消極的でした。 父と子は平成15年の別居から現在まで連絡や交流を欠いた状態です。
平成27年10月,養育費を月額各55,000円と増額するが支払終期の延長は認めない審判が出ました(つまり成人に達する日まで)。 この審判の半年後に,子が大学に進学したことを理由に,母が父に対し,収入に応じた学納金の分担と養育費の支払終期の延長を求めました。その請求はさいたま家裁川越支部で却下されたので,母が抗告しました。その抗告事件に対する判断が東京高裁で示されました。家裁と高裁と二つの判断には共通部分と相違点がありますので両方をここに示します。
(さいたま家裁川越支部の審判)
さいたま家裁川越支部は,大学の学費負担も,大学卒業までの養育費負担も認めませんでした。
(大学の学費の負担に関する家裁の判断)
※ この結論は高裁でも支持されました。
「・・・養育費の標準算定方式は生活保持義務に基づく適正妥当な養育費の算定を目的としており,15歳以上の子について公立高校の学校教育費を考慮しているものの,大学の学費のうち,上記の学校教育費を超える分については考慮していない。 これを超える大学の学費は,特別事情として,養育費の義務者が当該大学への進学を承諾している場合や,当事者の学歴,職業,資産,収入等に照らして義務者にこれを負担させることが相当と認められる場合に限り,養育費の算定に当たり大学の学費を考慮する必要があると解される。
これを本件でみると,前記の認定事実によれば,
1 父は,これまで子らの大学進学に対し,明示の承諾をした事実はなかったこと,
2 父は,平成25年春に子が私立大学の付属高校に進学する前に,母に対し,子が私立学校に進学することに反対し,母から進学費用の負担を求められたが応じなかったこと, 3 平成26年9月から平成27年10月まで係属した前件審判及びその調停手続では,子の大学進学が確定したことを根拠に母が養育費の増額と終期の延長を求めたが,父は私学進学に反対し,成人後の養育費の負担に消極的であったこと,
4 父と子らは,平成15年3月の別居から現在まで,連絡や交流を欠いた状態であったこと, が認められる。このような経過に照らせば,父において,子が大学に進学することを承諾していたとは認められない。
前記の認定事実によれば,父は,平成15年に母と離婚交渉をした際,「養育費は,子供名義の口座に,毎月指定日に,私と同じ学歴である大学卒業まで支払います。」「子供二人の養育費は毎月6万円を支払います。一人が大学を卒業後は毎月4万円を支払います。」と提案しており,父がこの時点では子らが大学に進学する事態を想定していたことがうかがえる。
しかし,前記の認定事実によれば, 1 上記の提案がされた当時,子は未だ5歳にすぎず,大学進学は十数年も先の話であったこと, 2 この提案は,父が不貞を認めて離婚条件を提案するという状況下で行われたが, 最終的には離婚交渉が成立せず,離婚訴訟が提起されるに至ったこと, 3 平成20年の離婚判決,平成21年に成立した家事調停,平成27年の前件審判では,いずれも養育費の支払終期を子の成人で区切っており,前件審判では終期の延長を求める母の申立が排斥されていること, 4 前記の提案の後,父は,再婚相手との間に2子をもうけ,当該女性と再婚する一方で,子らとは長年疎遠であるなど,家族関係をめぐる大きな変化が存在していたこと, 5 そのため,父は,母に対し,調停や審判の際,子が私立学校に進学したり,大学の学費や成人後の養育費を負担することに否定的であったこと, が認められる。 こうした経緯に照らせば,平成15年に父が母に対し,子の大学卒業まで養育費を支払うと提案していたとしても,それがその後も父の意向として存続していたとは認められず,前記の判断を妨げるものではない。
前記の認定事実によれば,父は私立大学を卒業して私立学校の教師として勤務し, 平成28年に約962万円と相当な額の収入を得ており,子は私立高校及び大学に進学するのに必要な学力を有していることが認められる。
しかし,母は平成26年の収入金額は約256万円(青色申告特別控除前の所得金額約1 3万円),平成28年の収入金額は約66万円(所得金額0円)にとどまること,父は本件の調停申立時に合計4名の未成年者に扶養義務を負い,現在も合計3名に対して負う状態にあり,子の数が少なくないこと,父と子らはこれまで14年以上も連絡や交流を欠き,父は母に対し,子の私学進学に反対し,大学の学費や成人後の養育費の負担について消極的であったことが認められる。 なお,母は平成22年9月に成立した調停において「子らにつき,病気,進学,その他特別な出費を要するときは,その都度,当事者間でその負担割合につき協議するものとする」と合意したと主張する。 しかし,上記の合意は,特別な出費を要するときに協議の機会を設けることを取り決めたにすぎず,父が将来における大学進学を承諾した趣旨とは解されず,前記の判断を左右するものではない。 以上によれば,母が,父に対し,子の通常の養育費を超えて,大学の学費について分担を求めることはできない。」
※ 詳細に事実認定をしたうえで判断を示しています。おそらくこの当事者間では何回も調停や審判が繰り返されていて相当に厳しい対立があって話合い解決が困難,きちんとした判断を示す必要があったという事情があったと推測されます。
(成人した大学生の通常の養育費に関する家裁の判断)
「養育費は,親が生活保持義務に基づき,未成熟子の養育に要する費用を負担するものであり,子が成人した後は,基本的に自己の労力等により生活すべき立場にある。 そこで,成人した大学生については,義務者が大学進学に同意している場合や,両親の学歴,職業,資産,収入等に照らして,大学への進学が相当であると認められる場合に,未成熟子として養育費を負担すべきものと解される。 本件で,父が子の大学進学に同意しているとか,諸般の事情に照らして子の大学への進学が相当であると認めるに足りないことは前記の認定と同様である(なお,本件の審判手続において,当裁判所は父に対し,養育費とは全く無関係に子との面会交流を実施することや,子の大学在学中は通常の養育費の支払を継続すること当の話合いを打診したが,父は一貫してこれを固辞する姿勢であった)。 したがって,母が父に対し,子が成人してから大学を卒業するまでの期間,通常の養育費を支払うよう求めることはできない。前件審判も同旨であり,その後の事情変更も認められない。」 ※ 家裁は,大学の学費と大学生の間の養育費について同じ様に扱って結論を出しました。高裁は大学の学費については家裁の結論を支持しましたが,大学在学中の養育費については「事情の変更」があるとして違う結論を導きました。
(東京高裁の決定)
※東京高裁は,大学の学納金については家裁の判断を支持して父の分担は認めませんでしたが,養育費の支払の終期の延長を認めました。 まず,大学の学費負担について高裁は次の様に述べて,大学の学納金を別居する父に負担させないとしました。
(大学の学費負担に関する高裁の判断)
前件審判時には高校生であった本人が大学生になり,現に通学し,成年に達した後も学納金及び生活費等を要する状態にあるという事情の変更があったということができる。 もっとも,大学進学のための費用のうち通常の養育費に含まれている教育費を超えて必要となる費用は,養育費の支払義務者が当然に負担しなければならないものではなく,大学進学了解の有無,支払義務者の地位,学歴,収入等を考慮して負担義務の存否を判断すべきである。 本件においては,父は本人が私立高校に進学することに反対し,本人の私立大学進学も了解していなかったと認められること,通常の養育費に含まれる教育費を超えて必要となる費用は本人が大学進学後は奨学金等による援助を受けたり,アルバイトによる収入で補填したりすることが可能と考えられること,母の収入はわずかであり父には扶養すべき子が多数いるという中で私立大学に進学した本人に対して奨学金やアルバイト収入で教育費の不足分を補うように求めることは不当ではないこと,前件審判時以降父と父の収入はほとんど変化がないこと,前件審判においては,通常の養育費として公立高校の学校教育費を考慮した標準算定方式による試算結果を一カ月当たり5,000円超えた額の支払が命じられていることからすると,父に対し,通常の養育費に加えて,本人が通学する私立大学への学納金にづいて,支払義務を負わせるのは相当でない。
(成人した大学生の通常の養育費に関する高裁の判断)
これに対し,前件審判において成人に達する日の属する月までとされた養育費の支払期間を大学卒業時である満22歳に達した後の最初の3月までに変更すべきかどうかは別異に考慮すべきである。 すなわち,父は,親として,未成熟子に対して,自己と同一の水準の生活を確保する義務を負っているといえること,本人は成人後も大学生であってん,現に大学卒業時までは自ら生活をするだけの収入を得ることはできず,なお未成年者と同視できる未成熟子であること,父は本人の私立大学進学を了解していなかったと認められるが,およそ大学進学に反対していたとは認められないこと,父は大学卒の学歴や高校教師としての地位を有し,年収900万円以上あること,父には本人の他に養育すべき子が3人いるとしても,そのうちの2人は未だ14歳未満であることに照らすと,父には,本人が大学に通学するのに通常必要とする期間,通常の養育費を負担する義務があると認めるべきである。 そして,父は母に対し,本人が大学に進学した後も成人に達する日の属する月まで毎月55,000円ずつの支払義務を負っていたから,毎月同額を本人が満22歳に達した後の最初の3月までの支払を命じるのが相当である。
(考察)
家裁は20歳までの養育費しか認めませんでしたが,高裁は,大学生になったことが事情の変更であるとしたうえで,いろいろな事情を考慮したうえで,大学の学費等は認めず,大学卒業までの間の養育費を認めました。考え方としては普遍性を持つものなので影響力は大きいと思います。しかし,あくまでも諸般の事情を考慮したうえでの個別事件に対する判断ですから,どんなケースでもこのように養育費の期間延長だけは認めてくれるとは限りません。また,このケースは離婚後も何回も調停審判が繰り返されていることが特徴的です。