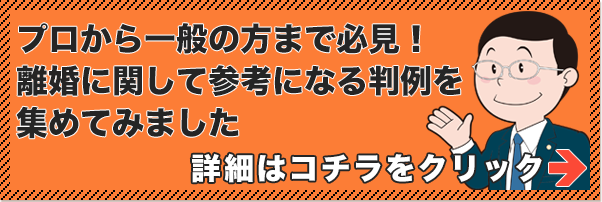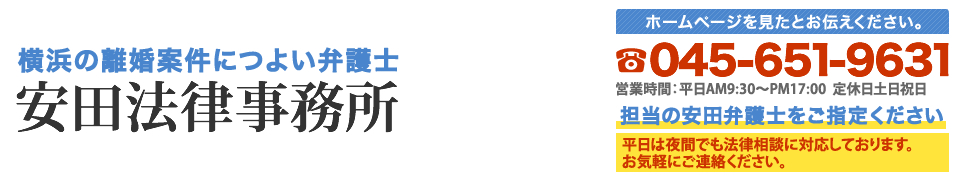最高裁平成29年12月5日決定(判例時報2365)
離婚後に、非親権者からは親権者変更が家庭裁判所に申し立てられ,親権者からは子の引き渡しの保全処分が民事訴訟手続で申し立てられたという事件について,最高裁の判断が示されました。
■事案
父と母は,平成22年に子が出来て婚姻しました。 平成25年に別居し,それ以後は母が子を監護養育していました。 平成28年に離婚しましたが,そのとき子の親権者は父親と定めました。 平成28年,母は父を相手として,親権者変更を求めて調停を申し立てました。 平成29年、父は母に対して,「親権に基づく妨害排除請求権」として「子の引渡仮処分命令申立事件」を民事訴訟として那覇地裁に提起しました。この仮処分命令申立事件が認められるかどうかが本件の大きな問題です。 一審の那覇地裁も二審の福岡高裁も,この仮処分命令申立事件の本案は家事事件である子の監護に関する処分の審判事件であり,民事訴訟の手続によることができないから,本件申立は不適法であるとして却下しました。それに対して許可抗告が申し立てられて最高裁の判断がなされました。
最高裁の判断
原審は,本件申立の本案は家事事件手続法別表第2の3の項所定の子の監護に関する処分の審判事件であり,民事訴訟の手続によることができないから,本件申立は不適法であるとして却下すべきものとした。 しかしながら,離婚した父母のうち子の親権者と定められた一方は,民事訴訟の手続により,法律上監護権を有しない他方に対して親権に基づく妨害排除請求として子の引渡を求めることができると解される(最高裁昭和35年3月15日,昭和45年5 月22日)。 もっとも,親権を行う者は子の利益のために子の監護を行う権利を有する(民法82 0条)から,子の利益を害する親権の行使は,権利の濫用として許されない。
本件においては,長男が7歳であり,母は父と別居してから4年以上、単独で長男の監護に当たってきたものであって,母による上記監護が長男の利益の観点から相当なものではないことの疎明はない。 そして,母は父を相手方として長男の親権者の変更を求める調停を申し立てているのであって,長男において,仮に父親に対し引き渡された後,その親権者を母に変更されて,母に対し引き渡されることになれば,短期間で養育環境を変えられ, その利益を著しく害されることになりかねない。 他方,父は,母を相手方とし,子の監護に関する処分として長男の引渡を求める申立をすることができるものと解され,上記申立にかかる手続においては,子の福祉に対する配慮が図られているところ(家事事件手続法65条等),父が,この監護に関する処分としてではなく,親権に基づく妨害排除請求として長男の引渡を求める合理的な理由を有することはうかがわれない。
そうすると,上記の事情の下においては,父が母に対して親権に基づく妨害排除請求として長男の引渡を求めることは,権利の濫用に当たるというべきである。 (分かりやすくするため文章は変えてあります)。
(裁判官木内道祥の補足意見)
親権は,子の監護及び教育をする権利であると同時に義務であって,子の利益のために行使されるべきものである(民法820条)。所有権が対象に対する排他的支配権であって,権利であるが故にその行使を妨害されないという妨害排除請求権が認められるのとは異なり,単に親権者であることからその親権の行使が認められるのではなく,その行使が子の利益のためにするものであってはじめて権利の行使として許容される。
親権の行使が「子の利益を害するとき」は民法834条の2による親権の停止の事由となり,親権そのものが停止さるに至るのであるから,親権を行使する個々の場面でも,子の利益を害するものが許されないことはいうまでもない。 個々と母のいずれが子を監護することが適切かを子の利益を基準として定め,適切な者への子の引渡を求める手続としては,家庭裁判所の子の監護に関する処分及びそれを前提とする保全処分という手続がある。この手続においては,子が15歳以上であれば必ずその陳述が聴取され(家事事件手続法152条2項,157条2項),子が15歳未満であっても,子の陳述の聴取,家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法によって子の意思の把握がはかられ,子の年齢及び発達の程度に応じて, その意思が考慮されなければならないのであり(同法65条),実務上,ほとんどの場合に,家庭裁判所調査官が関与し,子の意思の把握に大きな役割を果たしている。
さらに,子に意思能力があれば,裁判所は職権で子を利害関係人として参加させることができ,子の手続代理人として弁護士を選任するなどして子の意思を手続に反映させることも可能である(同法42条3項,23条2項)。このように,家庭裁判所は, 子の利益のために後見的な役割を果たすことがその職責とされているのである。
これに対し民事訴訟の手続による親権に基づく子の引渡請求の本案訴訟及びそれを本案とする民事保全処分においては,権利の存否及び保全の必要性について,もっぱら,当事者(本件でいえば,子の父と母)が裁判所に対して主張と証拠の提出を行わなければならず,裁判所が子の利益のために後見的役割を果たすことは予定されておらず,そのための道具立ては用意されていない。 父と母の間における子の引渡請求という紛争においては,子の利益という観点から,また,当事者の負担及び手続の実効性の観点からも,家庭裁判所における手続こそが本来的なものとして設けられているのである。
本件では,現在7歳となる子は,平成25年2月の別居以来,4年以上,母が単独で監護に当たっており(少なくとも本年3月末までは)母による監護について抗告人である父があらかじめ同意しており,その監護態様に異議が述べられたことがあるとは認められない。本件の申立においても,母による監護が子にとって不相当であるという疎明はされていない。
すると,そのような監護状態にある子を主たる監護者である母から引き離して抗告人(父)に引き渡すことは,抗告人が親権者であるとはいえ,子の利益を害するおそれがあるというべきである。 抗告人が家庭裁判所における子の監護に関する処分としての子の引渡を求めるのであれば,子の利益を害するおそれについて十分な審理を行った上での家庭裁判所の認定・判断が期待できるが,抗告人は,あえてその方法によることなく,民事訴訟の手続による親権に基づく子の引渡請求を本案とする民事保全処分としての子の引渡を求めているのであり,そのことからは,抗告人への子の引渡が子の利益を害するおそれがあることを否定する事由を見いだすことはできない。 このような抗告人の親権に基づく母に対する子の引渡請求は,子の利益のためにするものということはできず,権利の濫用として許されないものである。
(感想)
最高裁判決の補足意見というのは簡潔な判決文を詳しく解説したようなものです。 この事案では当然の結論でしょう。父の引渡請求を認めないという結論が高裁と変わらないのに最高裁が判断を示したのは,高裁の法的判断(子の引渡請求を民事訴訟法により求めることを不適法として却下した)をそのまま残すことが適切でないと考えたのでしょう。