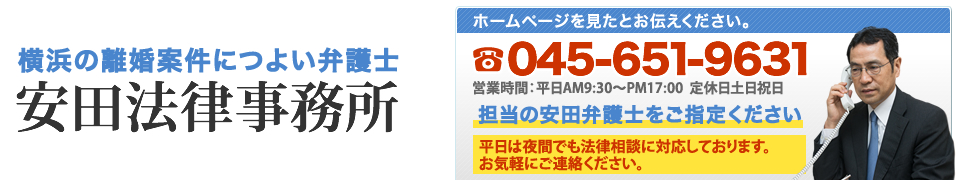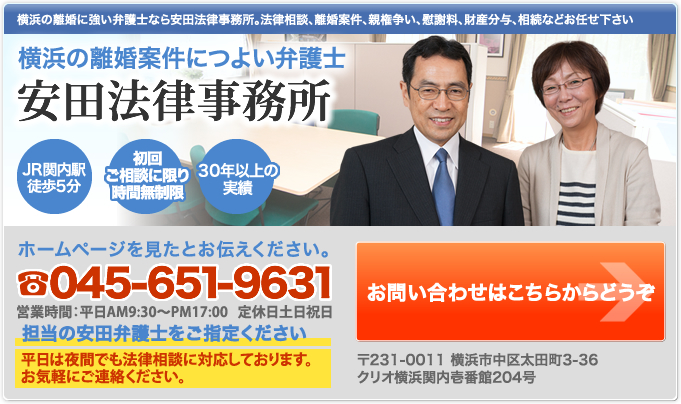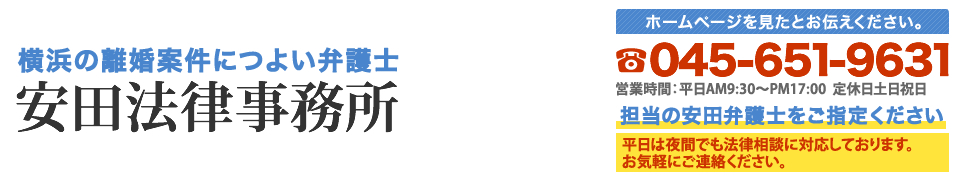離婚するときに発生する法的な問題点について説明します。
離婚するときの金銭問題 離婚するときに発生する金銭問題には次の5点があります。
1 離婚における財産分与とは?
民法768条は,「離婚をした者の一方は,相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と規定しています。
これを財産分与請求権と言います。
財産分与請求権には,
(1)婚姻中の夫婦の財産の清算,
(2)離婚に伴う損害の賠償,
(3)離婚後に困窮する配偶者の扶養
という3つの要素があります。
(1)婚姻中の夫婦財産の清算
夫婦が婚姻中に得た財産が離婚するときにも残っていたときは,その名義が夫名義であれ妻名義であれ,実質的には夫婦の共有財産と考えることができます。
しかし,離婚した後は生活が別々になるので,離婚するときに財産を清算して夫婦それぞれに分けるということです。
財産分与の割合
財産分与はほとんどの場合2分の1です。財産分与の比率が変わるのは,夫か妻が,普通の人とは違う特別に高い収入を得ていてそのために財産が形成された場合です。
夫が自営業で成功し普通の人よりもずっと高い収入を得て財産を残した場合,会社を興してその会社が成功し財産を築いた場合,医師や歯科医師あるいは病院経営によって特に大きな財産を築いたような場合などでは,特別の才覚によるものとして離婚における財産分与の割合が2分の1から修正される可能性があります。普通の夫婦や家庭では財産分与は2分の1ずつなのですが,このように夫の特別な能力等によって特別に大きな財産を形成した場合には,たとえば60%対40%などのように離婚における財産分与の割合が変更されることがあります。私の経験でも立証には苦労しましたが約6対4となった例が2回ありました。
専業主婦の財産分与割合
世帯の収入を稼いでいたのが夫だけで妻は専業主婦だった場合,離婚時に残った財産は夫が稼いだ金で買っています。だから夫の側からすると離婚するときに「これは俺の稼いだ金で買ったから全て俺のものだ。妻の金で買った物はない。」と感じられます。実際にそういうことを言う夫はよくいます。
しかし,妻が専業主婦である場合,外に出てお金は稼いでいませんが,家庭の中で炊事・掃除・洗濯などの家事をしたり子育てを担当して貢献しています。
妻が家事をしなかったら夫が自分で家事をするか,家政婦を雇う必要がありましたし,妻が育児をしなかったらシッターが必要でした。
妻が家事や育児を担当したから金銭を使う必要が無くなり財産が残ったのです。離婚のときには専業主婦にも財産分与は認められます。
財産分与の割合 離婚のときに認められる財産分与の割合は,専業主婦の場合でも2分の1となることが大部分です。
では共稼ぎ夫婦で妻が主婦であると同時に働いていたときは財産分与の割合がもっと増えるのかというと,まず変わりません。
財産分与の対象期間
財産分与は夫婦が婚姻中に形成した財産が対象です。婚姻中というのは,始期は婚姻届のときなるのが普通です。終期は別居など夫婦間の協力が無くなった時期で,その時を財産分与の基準時として,その日における預金の残高などが分与する財産の一つの基準になります。財産分与の基準時をいつにするかは離婚裁判における一つの争点となります。あまり明確でないときは双方の合意で決めるときもあります。
財産分与と特有財産・固有資産
結婚する前に夫や妻がそれぞれ自分で貯めた預貯金は,独身時代に一人で作った財産であって,夫婦の協力で作った財産ではないので離婚しても財産分与の対象外です。特有財産となります。
婚姻中であっても相続で得た財産や,親から贈与を受けた財産は,夫婦の協力で得た財産ではありませんから財産分与の対象にはなりません。
離婚のときに自分の特有財産・固有資産であると主張するためにはその証拠が必要です。結婚した当時の預金通帳や不動産を買った資金の出所の証明のために購入当時の預金通帳が必要になることもあります。
財産分与と退職金
離婚したときに既に退職金が入っていれば,それはそのまま財産分与の対象になります。ただし,結婚前からその会社に就職していたときは総在職期間よりも婚姻期間が短いので,支払われた退職金全額ではなく婚姻期間/在職期間の割合となります。
離婚するときには配偶者がまだ在職中であり,離婚した後に退職金が払われる場合には離婚から退職までの期間と退職金支払いの確実性などの状況によっては財産分与の対象になります。退職金は賃金の後払いという性質があるので退職金は基本的には財産分与の対象になると考えられているのです。
ただし,退職金は実際に退職するまでは手に入りませんしリストラ,倒産,懲戒解雇といった不確定要素もあります。離婚したときにすぐに払うのも困難です。そこで,離婚から退職までの期間や企業の安定性なども考慮したうえで財産分与の対象に含めて判断されることになります。普通は離婚から退職までの期間が数年間程度のときに問題にされることが多いですが10年あるから財産分与の対象にならないということもありません。家裁の調停や和解の実務では退職金が支払われるまで10年以上あっても裁判官からは財産分与に含めるように言われることが多いです。離婚判決になったときにもそういう判決を書くかどうかは分かりませんが。
なお勤務する会社に退職金規定がない場合は退職金もないので当然,離婚における財産分与の対象にもなりません。
財産分与と生命保険
離婚のときには生命保険も財産分与の対象となる場合があります。離婚のときには生命保険の満期が到来していなくても解約返戻金のある生命保険の場合は,生命保険を解約すれば一定のお金が返ってくるので預金と同じ性質があります。結婚中に保険料を支払っていた生命保険については解約返戻金相当の共有財産として財産分与の対象とされています。結婚する前から生命保険の保険料を支払ってきた場合は婚姻前の期間と婚姻後の期間を分けて,どれだけが財産分与の対象になるかを判断することになるでしょう。
生命保険の解約返戻金の金額は保険会社から書面で出してもらいそれを証拠として離婚を審理している家庭裁判所に提出することになります。
解約返戻金のない生命保険は財産分与の対象にはなりません。
離婚のときに生命保険の契約者を自分に変更して欲しいという希望もよくあります。離婚後の保険料は自分で払うからそれまでの生命保険を引き継ぎたいというものです。学資保険に多い希望です。
財産分与と宝くじ
高額の宝くじに当選した場合にそれを財産分与の対象とした高裁決定があります。
東京高裁平成29年3月2日決定は,宝くじの購入資金が婚姻後に得られた収入の一部である小遣いから拠出されたこと,宝くじ当選金が家族の自宅の借入金の返済や生活費にあてられていたことから,宝くじ当選金を原資とする資産は,夫婦の共有財産と認めました。
ただし,宝くじ当選金の購入資金は夫がその小遣いの一部を充てて宝くじ等の購入を続けたことにより当選し,これを原資として夫名義の預貯金,保険, 不動産,前渡金等,対象財産のほぼ全部が形成されたことから,財産分与対象財産の資産形成については,夫の寄与が大きかった,分与割合については,妻4,夫6の割合とするとしました。
分与すべき財産がないとき
財産分与は離婚したときに残った財産が対象ですから,離婚のときに財産が残って無ければ財産分与請求権も認められません。対象がなければ権利もないのです。
結婚後に形成した財産を全て一覧表にしたところ,借金の方が多くてマイナスになってしまえば財産分与も無くなってしまいます。
親の財産は財産分与とは無関係ですから配偶者の親がどんなに資産家であってもそれが財産分与に影響することはありません。
熟年離婚と財産分与
最近は50代,60代,あるいはそれ以上の高齢の方の熟年離婚も増えています。
熟年離婚は,子どもが成人しているので親権が問題にならない反面,不動産,預貯金,退職金など結婚してから夫婦で形成した財産が大きなものになっているので財産分与が大きな問題になります。現在残っている財産が明白だとしてもその取得費用の一部に固有財産(特有財産)が入っている場合にはその証拠が残っているかどうかが重要です。たとえば自宅不動産の購入資金の一部に結婚前の預金をあてたとか親から援助を受けたという場合です。熟年離婚の場合不動産を買ってから何十年も経っていることが多いので立証に困難をきたします。
目の前に迫った老後の生活がかかっていますから皆さん真剣ですし年金を取得する後の生活を想定できる年齢なので非常に切実です。積年の恨みをぶつける人もいますし反対に長年連れ添ってきたのだからお互いに老後を生きていけるようにしようという前向きな人もいます。人生の大きな転換点です。
財産調査
財産分与における大きな問題は,財産分与の対象となるべき財産を配偶者によって隠されてしまうことです。とくに離婚前に別居が先行すると記憶だけでもう何も分からなくなってしまいます。
離婚の調停や裁判になると預貯金などの財産については裁判所を通じて銀行や証券会社,保険会社に対して調査嘱託(裁判所を通じた情報収集制度の一つ)をすることも可能ですが,そのためには調査嘱託の対象になる金融機関の名前や支店が分からなければできません。もめる前にできるだけ具体的な財産資料を集めておかないと不利になります。離婚裁判でも何でも争いごとの最後は証拠の強さなのです。
離婚に伴う損害の賠償(財産分与の要素の一つ)
財産分与には慰謝料的要素を含めてもいいとされていますので,実質的には慰謝料を財産分与に含めて判断されることもあります。しかし,本来,慰謝料というのは精神的損害に対する損害賠償のことで,夫婦共有財産の清算が中心である本来の財産分与とは少し違うものです。
財産分与という名目で大きな慰謝料が請求できるということではなく,金額として融通がきくので調整要素としての性質が大きいかと思います。
離婚後に困窮する配偶者の扶養(財産分与の要素の一つ)
財産分与には離婚する配偶者に対する離婚後の扶養の要素を含めてもいいとされています。離婚によって収入の少ない配偶者の生活は大きく低下することが多いので扶養的要素を考えることは合理的なのです。しかし,あまり大きな期待はできません。これも財産分与の本質とはいえませんので離婚の審判や判決における調整要素としての性質が大きいと思います。
財産分与は2年以内
財産分与の請求は離婚のときから2年以内にしなければならないという短い期間制限があります(民法768条2項)。離婚と同時に財産分与も決めてあればいいのですが,事情があってとりあえず離婚だけ決めて籍を抜いてしまった場合には注意が必要です。
離婚すると生活が大きく変わりとても忙しいので2年間はアッと言う間に過ぎてしまいがちなのです。離婚届を出したらすぐに財産分与請求です。
財産分与と税
財産分与として不動産を配偶者に譲渡した場合は,財産分与をした方に譲渡所得税がかかるので注意が必要です。財産分与として金銭を渡した場合には譲渡所得税はかかりません。詳しくは税理士にお聞きください。当事務所で相談された方には当事務所から詳しい税理士をご紹介することもできます。
2 離婚と慰謝料(民法第710条)
離婚と慰謝料
慰謝料とは精神的な苦痛に対する損害賠償のことです。
離婚の場合では,慰謝料とは離婚について責任のある者が配偶者に対して支払うべきものです。離婚のときに慰謝料がするかどうかは離婚の原因が何かによって変わってきます。
不貞行為が原因で離婚する場合は不貞行為をした配偶者に離婚の責任がありますから慰謝料が発生します。配偶者のひどい暴力で離婚するときも慰謝料が発生するでしょう。しかし,性格の不一致で離婚するときはどちらに責任があるわけでもないので慰謝料は発生しません。離婚すれば必ず慰謝料が発生するわけではないのです。
また,現実には離婚さえしてくれればいい,何も要らないという切羽詰まった方もいらっしゃるので,法的に請求はできるけれども慰謝料なしで離婚という場合も発生することがあります。
慰謝料の金額
離婚事件を裁判にして判決になった場合,判決で認められる慰謝料の金額は世間で思われているほど(ネットに書かれているほど)高額ではありません。もともと日本においては慰謝料に対する評価が低いので離婚裁判でも高額になることは少ないです。判決で認められる慰謝料額は普通,100万から200万の間が多いでしょう。婚姻期間が長期に及ぶときは200万円を超えて300万円に近づくでしょうが,500万,1000万という高い慰謝料金額は特に報酬の高い方の場合以外は判決で認められることは極めて稀です。
慰謝料金額を高くするのはむしろ慰謝料を請求される相手の事情が大きく影響します。資力のある人が普通よりも高い金を払ってもいいから早く離婚したいという事情が慰謝料を引き上げることが多いです。ですから離婚事件でとくに高い慰謝料額を相手が受け入れるのは裁判よりも交渉や調停の方が可能性が高いです。
離婚の裁判で認められる慰謝料の金額は,離婚するまでの婚姻年数が何年か(10年,20年と婚姻期間が長いほど高額になります),離婚原因は何か,有責性の大きさ・悪質か,支払う人の資力などによって変わってきます。
また,裁判の場合は慰謝料の金額の1割を弁護士費用として上乗せすることが可能です。判決で慰謝料が認められればその認容された金額の1割が必要な弁護士費用として加算されることがあります。
離婚裁判と同時に不倫相手に対する慰謝料も請求できる
配偶者に不貞行為があるために離婚を請求するときに,同時に不貞行為の相手に対して慰謝料を請求するときは,同じ家庭裁判所で同時に提訴することができます。配偶者と不貞相手と両方に払わせたいときは別々に裁判をすることもできます。不貞相手に対する慰謝料請求(損害賠償請求)裁判は本来は地方裁判所の管轄する事件ですからこちらが原則の形でもあります。
離婚の原因となった事実によって発生した損害賠償請求事件(慰謝料の請求)は法律上,同じ家庭裁判所で審理することができるのです(17条)。
離婚と慰謝料請求事件の争点
配偶者や不貞相手に対して慰謝料を請求する場合,原告(訴えている人)が不貞行為の存在を立証する必要があります。多いのはホテルに入るところ出るところの写真です。最近はメールやラインの履歴もあります。メールやラインは不貞行為そのものではなく間接的なものですので不貞行為(肉体関係)の存在を直接示す内容であることが必要です。
訴えられた側の主張でよくあるのは,(1)不貞行為をしていない,(2)不貞行為はあったがそれは既に夫婦間の婚姻関係が破綻した後のことである,(3)(不貞相手から)相手が結婚しているとは知らなかった,です。(2)も(3)も客観的な事実から裁判所が判断することになります。
子どもから不貞相手に慰謝料請求できるか
これは昭和54年の最高裁判例がありその事件では否定されています。
判断した部分を紹介すると「父親がその未成年の子に対し愛情をそそぎ,監護,教育を行うことは,他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく父親自らの意思によって行うことかできるのであるから,他の女性との同棲の件か,未成年の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受けることかできず,そのため不利益を被ったとしても,そのことと女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならない」・・・
「妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が,妻子のもとを去った男性と同棲するにいたった結果,その子が日常生活において父親から愛情をそそがれ,その監護、養育を受けることができなくなったとしても,その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り,女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではない。」
したがって,単なる不貞行為だけでは子どもに対する不法行為とはなりません。不貞にとどまらず何かもっと積極的な悪意のある行為がないと子どもから不貞相手に対する慰謝料請求はできません。
姑に対して慰謝料請求できるか
この点について判断した昭和53年の名古屋地裁一宮支部の判決があります。
裁判所は判決の中で,姑は嫁に対し悪罵,干渉を行い,夫もこれを抑制するどころか同調して妻(嫁)の努力を認めず反抗すると直ちにその両親を呼びつけて親族ともども一方的に非難していたもので,このような事情のもとでは嫁が家庭生活の中で陽気になりえようはずも無く,その後の別居にいたる経過をみると,夫と姑のこの所為は婚姻を継続しがたい重大な事由にあたる。そして,夫と姑に対し,嫁(妻)に200万円の慰謝料を支払うよう判決しました。
これは姑と夫との共同不法行為により離婚になったのでその責任を二人が負うということを認めたものと思われます。したがって,あまりひどい嫁いびりがそれが離婚原因にまでなると姑の責任もありえます。
3 離婚までの生活費(婚姻費用)
離婚する前に夫婦が別居すると,それまでは夫婦が共通して生活費を出していたところ生活が別々になるので,日々の生活費をどうするかという問題がでてきます。
夫婦双方に充分な収入があれば大きな問題にはなりませんが,夫婦の収入に大きな格差があり,自分の収入では生活ができないときは,離婚するまでの期間,収入の多い配偶者から生活費を払ってもらうことができます。これを婚姻費用といいます。
離婚してからの養育費というのは子どもの生活費のことですが,婚姻費用は離婚するまでの家族の生活費のことです。
婚姻費用には,配偶者の生活費と子供の生活費が含まれます。
このうち子供の生活費は離婚後も養育費として存続しますが,配偶者の生活費は離婚した時点で扶養義務が終わるので終了します。
婚姻費用の金額
婚姻費用の金額は夫婦双方の収入、子供の年齢や人数などによって決まります。
家庭裁判所には婚姻費用の算定表があり,特別の事情がなければその算定表にしたがって婚姻費用の金額が決まります。
婚姻費用の算定表は当事務所にもありますしインターネットで公開されています。
生活費が不足すると直ちに生活に困るので婚姻費用分担調停の手続は家庭裁判所でも早く進めてくれるものです。 婚姻費用の算定表は2019年12月に改訂されたので新しい算定表と古い算定表を間違えないようにしてください。
収入の多い配偶者としては,配偶者が自分で出て行ったのに生活費を要求されて気持ちのいいものではないかもしれません。
しかし,離婚せずに夫婦でいる間に婚姻費用を払わないと夫として,父としての法律上の義務を果たさないと見られることになり,離婚の裁判で裁判官に不利な心証を取られる危険があります。法律上の義務はきちんと果たしておくべきです。
4 養育費
養育費算定表
婚姻費用は離婚が成立するまでのことですが,離婚した後は未成年の子供の養育費が問題になります。
養育費の金額は別れた夫婦双方の収入や子供の年齢,人数によって一定の基準があります。養育費についても家庭裁判所では養育費算定表を使用しており,基本的には算定表の範囲内の金額となります。なお、算定表は2019年12月に改訂されて新算定表となっています。古い算定表と間違えないように注意してください。
算定表が前提としている通常の費用ではない特別に費用がかかる特別な事情があるときは算定表の範囲を超えて修正されることがあります。子どもが特殊な病気のためにどうしても特別の医療費や生活費がかかる場合などです。単に贅沢な生活をしているだけでは駄目です。養育費の色々な事例についてはブログに詳しく掲載していますので参照してください。
養育費と私学への進学費用
家庭裁判所の養育費に使用されている算定表には,公立学校の学費まで含まれています。しかし,私立の学校の学費は公立よりも高いので離婚後の通常の養育費だけでは進学させるのが困難です。そういう場合,私学の学費などまで養育費として離婚した元配偶者に請求できるのでしょうか。
離婚した元夫(妻)が子どもの私学への進学を認めていたかどうかが重要です。元夫(妻)が私学への進学を認めていれば養育費にプラスして私学の費用の分担を求めることは可能です。明確に私学への進学を認めていない場合は,私学進学を前提とする行為をしていたか,私学に在籍していることを前提にした婚姻費用を払ってきたかなどの間接事実によって家庭裁判所で判断されることになります。
離婚した元夫(妻)が子どもの私学進学を認めていた場合には、私学進学にかかる費用について両親で分担することになります。そのときは養育費と同様に両親の収入が基準となります。
養育費と医学部への進学費用
子どもが医学部に進学した場合は普通の大学よりもずっと高い学費がかかります。
その負担を養育費として請求することができるでしょうか。
これも離婚した元夫(元妻)が医学部への進学を認めていたかどうかが問題になります。子どもが医学部に行くような家庭では親も医者であったり高額所得者であることが多いし,子どもが医者になるということは嬉しいことなので絶対に払わないという争いになることは少なく交渉案件であるように思います。ただし,金銭的な余裕がない場合は色々な奨学金や医学部生だけの奨学制度を利用することも行われています。両親の間で負担の押し付け合をするのではなく,子どもが両親と相談して現実的で可能な方法を探っていくべき場面です。
離婚後に再婚し養子縁組した場合と養育費
子どもの親権者となった監護親が再婚してその再婚相手が子どもと養子縁組した場合,養育費は変わるのかという問題については平成29年に福岡高裁が出した決定があります。
福岡高裁は,養子縁組の制度は未成年者の監護養育を主たる目的としていて,養子縁組は子の福祉と利益のためにその扶養も含めて養育を全面的に引き受けるという意思のもとにしたのであるから,子に対する扶養義務は第一次的に養親にある,実親は養親において十分に扶養の義務を履行することができない場合に限って扶養義務を負う。実親の資力が養親らの資力よりも高いからといって実親に対してその差を埋め合わせるための金額を請求することはできない。
そして,親の再婚に伴い子が親権者の再婚相手と養子縁組をした場合は子の養育費を見直すべき事情に当たる。と判断しました。
したがって,監護親が再婚してその再婚相手が子どもと養子縁組した場合は,既に決まっている養育費を見直す事情になります。子どもはまず養親が扶養するもので実親の義務は二次的な扶養義務となります。
養育費を払う人が失業した場合
離婚した後の養育費は両親の実際の収入を養育費算定表に当てはめて決められます。養育費を一度決めた後に養育費を払う人が失業した場合どうなるのでしょうか。この点は東京高裁の判決が参考になります。
養育費は,当事者が現に得ている実収入に基づき算定するのが原則である。
養育費支払い義務者が無職であったり,低額の収入しか得ていないときは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される場合に初めて,義務者が本来の稼働能力(潜在的稼働能力)を発揮したとしたら得られるであろう収入を諸般の事情から推認し,これを養育費算定の基礎とすることが許される。
養育費支払い義務者の潜在的稼働能力に基づく収入は,退職理由,退職直前の収入,就職活動の具体的内容とその結果,求人状況,職歴等の諸事情から判断する。
養育費支払い義務者が失職した直後から従前の収入と同程度の収入が得られたはずであるという判断は,退職する必要もないのに辞職したというような例外的な事情がある場合でなければできない。
養育費支払い義務者が失職した直後から直ちに潜在的稼働能力に基づく収入を算定することが相当でないのであれば,それが相当でない期間は,雇用保険による実収入について審理し,これを養育費算定の基礎とする必要がある。
以上が高裁の判断です。失業した理由や求職状況等から「潜在的稼働能力」を発揮したであろう収入を推認できる場合もあるでしょうが、特別の事情がなければ失業手当てを基準とすることになりそうです。実際には養育費の調停には時間がかかり失業しても早く再就職している人が多いので,失業したままで問題になることは少ないのだろうと思われます。
5 離婚後の年金分割
離婚時に厚生年金や共済年金の年金分割ができます。夫が自営業で国民年金だと年金分割は関係ない話になります。
厚生年金の年金額が,働いていた人の就労期間や賃金の金額を基にして決まるため,中高齢者が離婚すると,、現役時代の男女の雇用格差(夫が勤務を続け妻が退職することが多いこと),給与格差(男女ではまだ賃金格差が大きい)のために,離婚後の夫婦の年金取得額が大きく違ってしまうという問題を解決するための制度です。
離婚後に年金分割の対象となるのは「厚生年金や共済年金の報酬比例部分」(いわゆる二階部分)で,そのうち婚姻期間中の夫婦の厚生年金保険料納付記録を離婚した場合に当事者で分割することが認められます。
夫が厚生年金か共済年金の場合で,婚姻期間中に夫が長期間,勤務していたために,夫が受け取る年金額と妻が受け取る自分の年金額が大きく違う場合には非常に役に立ちます。ただ,夫が受け取る年金の半分の金額をもらえるわけではありません。
離婚するときに夫婦で年金分割について話合いがつかない場合は調停や審判を利用する必要が出てきます。
この制度が始まる以前の時期に年金を納めた部分について分割割合をどうするかという問題が残っています。夫婦の合意で割合を決めて分割することになりますが,合意が出来ないときは家庭裁判所が分割割合を決めてくれます。
そして,申し立てればほぼ自動的に裁判所が2分の1の分割割合を認める扱いが多いです。
なお,年金分割を求めていくには「年金分割のための情報通知書」を年金事務所で取得しておくことが必要です。これを先に用意しておきましょう。
ただあまり早く入手しすぎて調停等に時間がかかると取り直しになってしまうこともあります。
まとめ
離婚のときの財産分与,慰謝料,婚姻費用,養育費などについて説明してきました。ここに書いてあることは一般論であって実際のケースの一つ一つで違います。できるだけ早く弁護士の法律相談を受けることをお勧めします。
以下にも知っておきたい法律問題をまとめてますので、合わせてご参照ください。