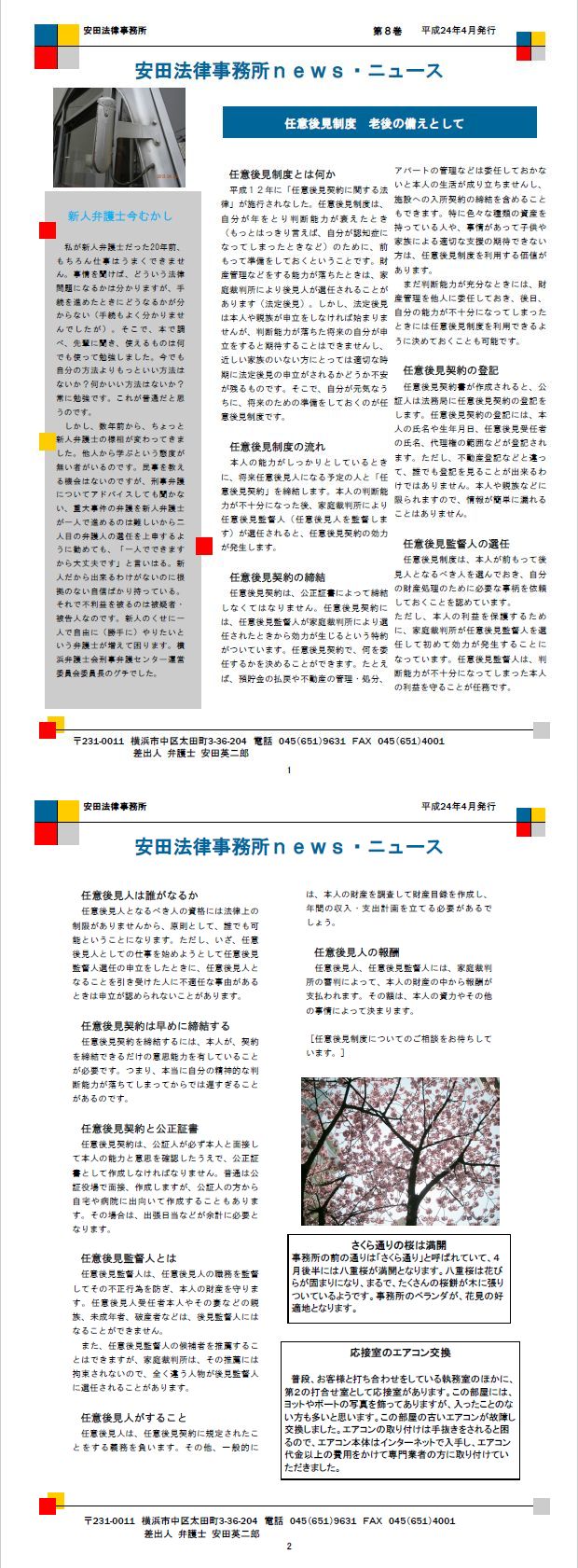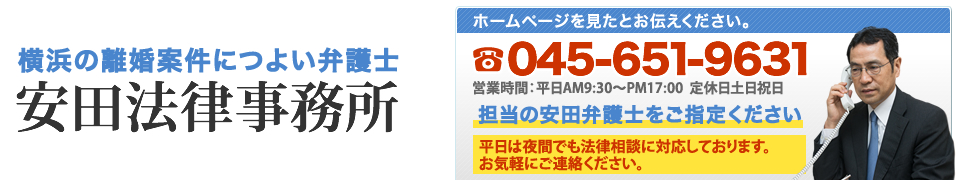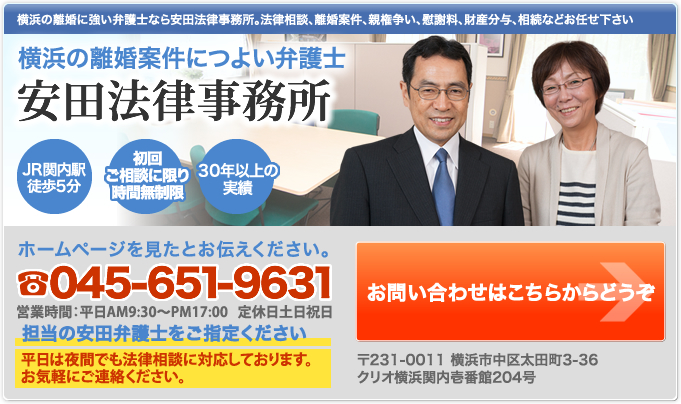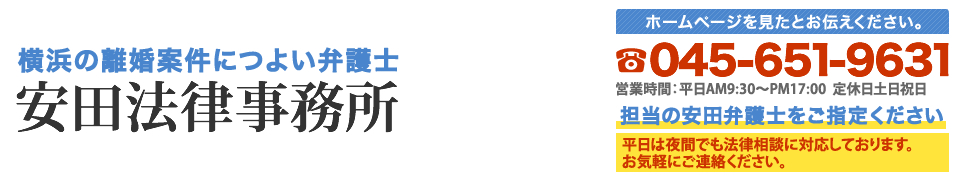任意後見制度とは何か
平成12年に「任意後見契約に関する法律」が施行されました。任意後見制度は、自分が年をとり判断能力が衰えたとき(もっとはっきり言えば、自分が認知症になってしまったときなど)のために、前もって準備をしておくということです。財産管理などをする能力がおちたときは、家庭裁判所により後見人が選任されることがあります(法定後見)しかし、法定後見は本人や親族が申立をしなければ始まりませんが、判断能力がおちた将来の自分が申立をすると期待することはできませんし、近しい家族のいない方にとっては適切な時期に法定後見の申立がされるかどうか不安が残るものです。そこで、自分が元気なうちに、将来の為の準備をしておくのが任意後見制度です。
任意後見制度の流れ
本人の能力がしっかりとしているときに、将来任意後見人になる予定の人と「任意後見契約」を締結します。本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所により任意後見監督人(任意後見人を監督します)が選任されると、任意後見契約の効力が発生します。
任意後見契約の締結
任意後見契約は、公正証書によって締結しなくてはなりません。任意後見契約には、任意後見監督人が家庭裁判所により選任されたときから効力が生じるという特約がついています。任意後見契約で、何を委任するかを決めることができます。たとえば、預貯金の払戻や不動産の管理・処分、アパートの管理などは委任しておかないと本人の生活が成り立ちませんし施設への入所契約の締結を含める事もできます。特に色々な種類の資産を持っている人や、事情の期待できない方は、任意後見制度を利用する価値があります。まだ判断能力が十分なときには、財産管理を他人に委任しておき、後日、自分の能力が不十分のなってしまったときには任意後見制度を利用できるように決めていくことも可能です。
任意後見契約の登記
任意後見契約書が作成されると、公証人は法務局に任意後見契約の登記をします。任意後見契約の登記には本人の氏名や生年月日、任意後見受任者の氏名、代理権の範囲などが登記されます。ただし、不動産登記などと違って、誰でも登記を見ることが出来るわけではありません。本人や親族などに限られますので、情報が簡単に漏れることはありません。
任意後見監督人の選出
任意後見制度は、本人が前もって後見人となるべき人を選んでおき、自分の財産処理の為に必要な事柄を依頼しておくことを認めています。ただし、本人の利益を保護するために、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が発生することになっています。任意後見監督人は、判断能力が不十分になってしまった本人の利益を守ることが任務です。
任意後見人は誰がなるのか?
任意後見人となるべき人の資格には法律上の制限がありますから、原則として、誰でも可能ということになります。ただし、いざ、任意後見人そしての仕事を始めようとして任意後見監督人選任の申立をしたときに、任意後見人をなることを引き受けた人には不適任な事由があるときは申立が認められないことがあります。
任意後見契約は早めに締結する
任意後見契約を締結するには、本人が、契約を締結できるだけの意思能力を有していることが必要です。つまり、本当に自分の精神的な判断能力がおちてしまってからでは遅すぎることがあるのです。
任意後見契約と公正証書
任意後見契約は、公証人が必ず本人と面接して本人の能力と意思を確認した上で、公正証書として作成しなければなりません。普通は公証役場で面接、作成しますが、公証人の方から自宅や病院に出向いて作成することもあります。その場合は、出張日当などが余計に必要となります。
任意後見監督人とは
任意後見監督人は、任意後見人の職務を監督してその不正行為を防ぎ、本人の財産を守ります。任意後見人受任者本人やその妻などの親族、未成年者、破産者などは、後見監督人にはなることが出来ません。また、任意後見監督人の候補者は推薦することはできますが、家庭裁判所は、その推薦には拘束されないので、全く違う人物が後見監督人に選任されることがあります。
任意後見人がすること
任意後見人は、任意後見契約に規定されたことをする義務を負います。その他、一般的には、本人の収入・支出計画を立てる必要があるでしょう。
任意後見人の報酬
任意後見人、任意後見監督人には、家庭裁判所の審判によって、本人の財産の中から報酬が支払われます。その額は、本人の資力やその他の事情によって決まります。
[任意後見制度についてのご相談をお待ちしています]
新人弁護士今むかし
私が新人弁護士だった20年前、もちろん仕事はうまくできません。
事情を聞けば、どういう法律問題になるかは分かりますが、手続きを進めた時にどうなるかが分からない(手続もよく分かりませんが)そこで、本で調べ、先輩に聞き、使えるものは何でも使って勉強しました。
今でも自分の方法よりもっといい方法はないか?
何がいい方法はないか?常に勉強です。これが普通だと思うのです。
しかし、数年前から、ちょっと新人弁護士の様相が変わってきました。
他人から学ぶという態度が無い者がいるのです。
民事を教える機会はないのですが、刑事弁護についてアドバイスいていても聞かない、重大事件の弁護を新人弁護士が一人で進めるのは難しいから二人目の弁護士を選任を上申するように勧めても、「一人でできますから大丈夫です」と言いはる。
新人だらか出来るわけないのに根拠のない地震ばかり持っている。
それで不利益を被るのは被害者・被告人なのです。
新人のくせに一人で自由に(勝手に)やりたいという弁護士が増えて困ります。
横浜弁護士会刑事弁護センター運営委員会委員長のグチでした。
さくら通りの桜は満開
事務所の前の通りは「さくら通り」と呼ばれていて、4月後半には八重桜が満開をなります。
八重桜は花びらが固まりになり、まるで、たくさんの桜餅が木に張り付いているようです。
事務所のベランダが、花見の好適地となります。
応接室のエアコン交換
普段、お客様と打ち合わせをしている執務室のほかに、第2の打ち合わせ室として応接室があります。
この部屋には、ヨットやボートの写真を飾ってありますが、入ったことのない方も多いと思います。
この部屋の古いエアコンが故障し交換しました。
エアコンの取り付けは手抜きをされると困るので、エアコン本体はインターネットで入手し、エアコン代金以上の費用をかけて専門業者の方に取り付けて頂きました。